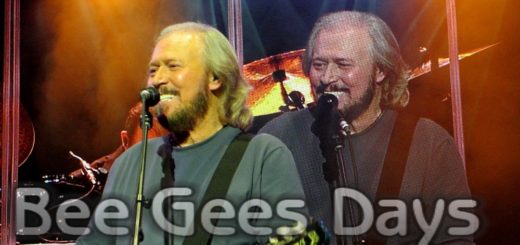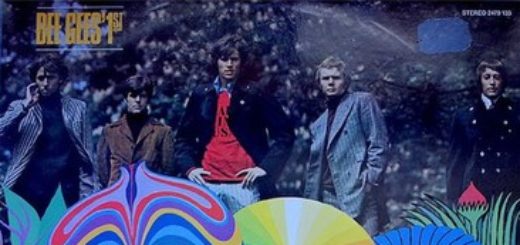【2025年8月】「兄弟愛のグループ ビー・ジーズ」(前編)
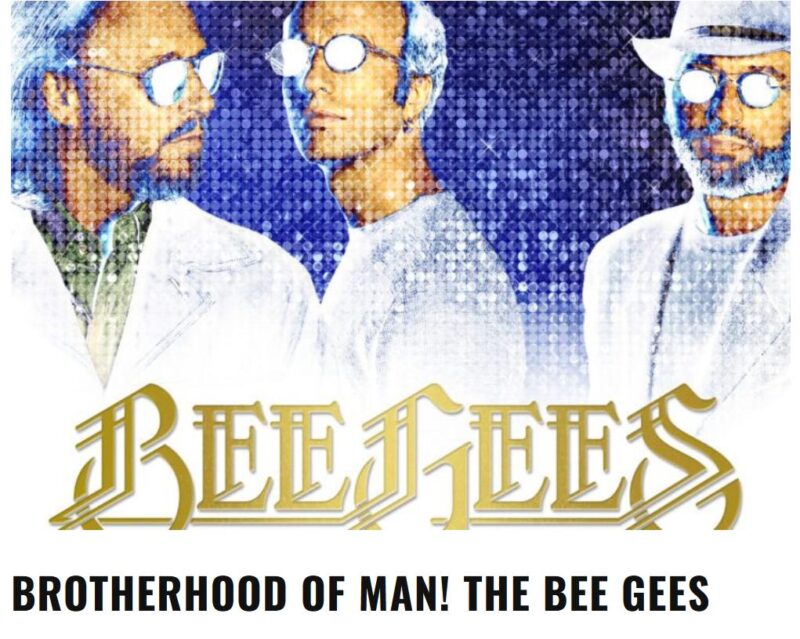
バリーの誕生日である9月1日を前にして、アメリカの音楽誌『Music Connection』にビー・ジーズに関する内容の濃い記事が掲載されました(オンライン版2025年8月28日付)。題して”Brotherhood of Man!The Bee Gees”。ちょっと長い記事なので前・後編に分けて、ざっと内容をご紹介します。
9月1日はバリー・ギブの誕生日だ。この8月に、HBOドキュメンタリー・フィルムズ制作の『ビー・ジーズ 栄光の軌跡(The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart)』を観た。バリー、モーリス、ロビンのギブ兄弟、すなわちビー・ジーズの栄光と困難の軌跡をたどった長編ドキュメンタリー映画だ。
1960年代にすでに有名だったこの草分け的なトリオは、キャリアを通じて1,000を超える数の曲を書き、20曲のナンバーワン・ヒットを生み出し、時代のテイストやスタイルが変遷するなか50年の長きにわたって活躍し続けた。
ビー・ジーズは、22枚のスタジオ・アルバムと数々のサウンドトラック(大成功を収めた『サタデー・ナイト・フィーバー』を含む)をレコーディング。印象的で個性的なスリー・パート・ハーモニーを特徴とする世界的ヒットを数十曲も飛ばして、ポップカルチャーに多大なインパクトを与えた。ビルボード誌のホット100チャートでは、『サタデー・ナイト・フィーバー』収録の「愛はきらめきの中に」「恋のナイト・フィーヴァー」「ステイン・アライヴ」をはじめとする9曲のナンバーワン・ヒットと23曲のトップ10ヒットを達成したほか、「傷心の日々(How Can You Mend A Broken Heart)」「ジョーク」「ロンリー・デイ」「ワーズ」「ユー・ウィン・アゲイン」など数多くの名曲で世界中のチャートを賑わせた。
映画『ビー・ジーズ 栄光の軌跡』は2020年12月にHBOで初放映され、その後HBO Maxで配信されている。(訳注 アメリカでの話です)
フランク・マーシャル(『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』『シービスケット』『ビーチ・ボーイズ』)が監督、ナイジェル・シンクレアとジャンヌ・エルファント・フェスタ(HBO『アポロ』およびHBO『ジョージ・ハリスン: マテリアル・ワールド』)がプロデューサーとして制作にあたった本作は、HBO広報のニュースリリースにいわく、「内容の濃い長兄バリーのインタビューと、亡くなったふたごのロビン&モーリスのアーカイヴ映像を交えて、ギブ・ファミリーの物語を深く掘り下げたドキュメンタリー」だ。
レコーディング・セッション、コンサート、テレビ出演、ホームビデオなどこれまで未公開だった貴重なアーカイヴ映像が数多く収められているほか、エリック・クラプトン、ノエル・ギャラガー、ニック・ジョナス、クリス・マーティン、ジャスティン・ティンバーレイク等のミュージシャン、音楽プロデューサーのマーク・ロンソン、歌手のルル、RSOレコード幹部のビル・オークスをはじめとする大勢の関係者のインタビューも収録されている。
『Vulture』誌や『New York』誌のテレビ評論家ジェン・チェイニーは、2020年12月11日付の『TV REVIEW』誌のレビューで、「HBO の新作ドキュメンタリー『ビー・ジーズ 栄光の軌跡』を見れば、ビー・ジーズの物語、ビー・ジーズの才能や影響力には、ディスコの王者というような単純化されたイメージをはるかに超えた深みと幅があることがわかる」と絶賛している。
ビー・ジーズはロックの殿堂、ソングライターの殿堂、BMIアイコンズ、ボーカル・グループの殿堂、さらにはダンス・ミュージックの殿堂において、殿堂入りを果たしている。
小説家ダニエル・ワイズマンは、「私はビー・ジーズを、ゴフィン/キング、レノン/マッカートニー、フェイゲン/ベッカー等、20世紀の偉大なソングライティング・チームの系譜に位置づける」と2002年付けの電子メールの中で総括してくれた。
もし彼らが単なる歌うグループ、ときとして馬鹿にしたように「ディスコに転向したオーストラリアのボーイバンド」と呼ばれるような存在に過ぎなかったなら、西洋文化では半数の人がビー・ジーズの曲を少なくとも3曲は何も見ないで歌える、というような事態は起こりようがなかった。彼らは曲を書き、歌った。思いを、秘められた意味を、心を、そして驚きをこめて。そして彼らが70年代のニューヨークという都会の混沌に衝撃を受け、異邦人の無垢な眼差しを向けたとき、まるで魔法のように生み出されたのが今という時代の普遍的な肖像だった。
彼らの先駆者としての功績も認めるべきだ。文化全体が西へと向かっていたときに、ビー・ジーズは、賢明にも、アリフ・マーディンとともに、東へ、マイアミへと向かい、ダンスミュージックに取り組んだ。このジャンルに対する深い敬意があったからこそ、あれだけの成功を成し遂げることができたのだ。ティーナ・マリーのように、(そして大勢のブルーアイド・ソウルの歌い手とは違って)ビー・ジーズのディスコは実際にダンスフロアでも愛されたのである。
マン島育ちの三人の若者にしては悪くない。『メイン・コース』が発表されてからの5年間というもの、他の白人ロック・アーティストもこぞってディスコのレコードを作ろうとしたが、中にはゲゲッとするようなレベルのものもあり、ビー・ジーズのように自然体を保ったものはひとにぎりにすぎなかった。
伝説によれば、ギブ兄弟は『土曜の夜の部族の儀式(訳注 後の『サタデー・ナイト・フィーバー)』という低予算映画のための楽曲の大半を、大まかなあらすじぐらいしか知らない状態で、フランスのエルヴィル村にこもってわずか1週間足らずで書き上げたという。他のソングライティング・チームにこの仕事を任せられただろうか? きっと悲惨な結果になったにちがいない。けれどもビー・ジーズの血脈の奥深くには、ダンスミュージックの、ハッスルの、ニューヨーク・タイムズが人間に与える影響の、その真髄が宿っていた。だからこそ彼らがこの企画に命を吹き込んだのだ。
あまりに有名になるとホルマリン漬け状態のようになることがある。エリザベス・テイラーやマイケル・ジャクソンのように、大騒ぎされるだけで実際の芸術性が見失われ、現象ばかりが前面に出てしまう。ところがビー・ジーズはさらに書き続けた、忘れがたいキャッチーで感動的な曲を書き続けた。ビー・ジーズを嫌う馬鹿者どもが多いはずだ。彼らはそれほどすごかったからだ。
カリフォルニア大学ロサンジェルス校ハーブ・アルパート音楽学校のデイヴィッド・リーフ准教授は、「音楽史上最高のグループの名前を挙げるなら必ずビー・ジーズも入れるべきです。何しろ、あのハーモニー、そして曲の持つ圧倒的な質と量だ」と、2020年に当方が行ったインタビューでこう証言してくれた。
「1967年から彼らのファンで、一緒に仕事をする機会にめぐまれ、オフィシャル・バイオグラフィを書いたり、ビー・ジーズのグラミー賞トリビュートでは回顧企画の制作を担当することができました。中でも素晴らしかったのは、長編ドキュメンタリー『This Is Where I Came In』(訳注 2001年発表の本作は『The Official Story of the Bee Gees』としても知られています)で彼らの物語を語る役割を任されたことです」
2020年にリーフ氏に取材した際に、彼が書いたビー・ジーズのオフィシャル・バイオと、2001年制作(訳注 この記事の原文では「2010」年となっていますが、単純なミスでしょう)のドキュメンタリー『This Is Where I Came In』について聞いてみた。
「1978年の春、僕が書いたブライアン・ウィルソンの伝記『The Beach Boys and The California Myth』はまだゲラ刷りの段階だったのですが、これがビー・ジーズの公認伝記を書く人間を探していたRSOレコード(当時のビージーズのレーベル)の幹部だったジェイ・レヴィの目に留まったんです」
そこでビー・ジーズの伝記を書く仕事を任されることになり、夏にマイアミへ飛んで作業を開始しました。ビー・ジーズの3人全員、夫人たち、ロバート・スティグウッド、アンディ・ギブ、そして両親にもインタビューを重ねて伝記を執筆し、1979年に発表しました。その後も20世紀末まで、ビー・ジーズと組んでさまざまなプロジェクトを行いましたが、中でも大きかったのはビー・ジーズのロックの殿堂入りの仕事でしょうか。
1990年代には、いろいろな音楽ドキュメンタリーや回顧番組の仕事をするようになったので、僕にすればごく自然にビー・ジーズのドキュメンタリーを作りたいと思うようになりました。一緒の仕事を通じて彼らとの間には信頼関係ができていましたが、それこそドキュメンタリー作りには欠かせないものでしたからね。たぶん、当時彼らのマネージャーだったキャロル・ピーターズが最初にこの企画を持ち込んでくれたんだったと思うのですが、幸い、A&Eの『バイオグラフィ』シリーズが、これなら2時間スペシャルにうってつけのテーマだと評価してくれました。
単純な話、『This Is Where I Came In』が成功しているのは、ビー・ジーズのファミリー・ヒストリーが音楽史に残る偉大な物語だからなんですよ。彼らは史上もっとも愛されている作品群の作者というだけでなく、カメラを前にした存在感と逸話の語り口が素晴らしい。よっぽど無能でもないかぎり、ビー・ジーズの伝記作品を作って駄作になるはずがないんですが、それでもこれは傑作だと僕は自認しています。
この作品が大勢に喜んでもらえたのは素晴らしい。特にビー・ジーズの大ファンというわけでもなかった人も『途中で止められずに最後まで観てしまった』と言ってくれたのがうれしかったです。みんな『以前よりずっと、ビー・ジーズって素晴らしい、いいなあと思うようになった』と言ってくれました。これは僕にとって大きな意味のあることでした。自分が大好きなアーティストについて作品を作る目的のひとつは、熱心なファンに喜んでもらうことだけではない。もっと大切なのは新しいファンを生み出すことだからです。
この映画では、ギブ兄弟との数十年にわたる関係が有利に働きました。三人には競争意識があって、自分がなるべく長く画面に映りたいっていう感じでした。そのためには、鋭い切り口の発言をするか、面白い逸話を披露するかです。こういうのは珍しい。もうひとつ大切なのは、この作り手なら編集段階でちゃんと守ってくれるという信頼感を持ってくれていることです。そうなれば、さらに突っ込んだ話をしてくれますから。
僕は、1978年1月21日付けの『メロディ・メーカー』誌にビー・ジーズのインタビュー記事を書きました。タイトルは「いかにビー・ジーズがアメリカを掌中にしたか」です。僕は70年代に彼らのコンサートを何回か観ました。1971年にはオーケストラを伴った公演を観たし、カリフォルニア州バーバンクで行われたNBCテレビの『ミッドナイト・スペシャル』の収録にも立ち会いました」
❝ロビン・ギブはベネディクト・キャニオンに借りていた家で話してくれた。『ビー・ジーズが成功した理由のひとつは僕たちが音楽を演説の手段にしていないからです。
僕が信じているのは、音楽は人を現実からはなれた場所へ連れていってくれるということ、しかもその音楽に共感するかどうかも聞く人にゆだねられている、ということです。歌を通して人と人が結びつけば、何かが起こるんです。
例えば『愛はきらめきの中に』。あの曲では、歌われているのが男性なのか女性なのかもはっきりさせていません。普遍的なニュアンスにしてあるので、誰の心にでも響く。レコーディングする前から、この曲には人間としての僕たち自身を入れることができる、という気がしていました。愛はつなぎとめてくれる錨であり、ベースです。僕らの曲は軽やかで爽やかなものばかりじゃない。前にも言ったことがあるけれど、とにかく僕たちは曲を書く側の人間です。解釈する側じゃない。10年前には社会に抗議する音楽が主流だった。僕たちはその型にはまったことは一度もない。流行に飛びつくこともなかった。この10年で数々の流行を見てきました。フラワーパワーに、グリッター……。音楽を通して豊かな愛を表現できる、音楽は人と人を結びつける触媒なんだということを、ビー・ジーズはこれまでずっとわかってきていたと思います』
また、バリー・ギブはこう話してくれた。「モーリスはより難しいパート、ファルセットを歌っています。僕たち、以前は安全に厳密に演奏していました。オーケストラをクッション役にしてね。確かにきれいではあったんですが、自分たちの能力に負荷をかけていなかったと思うんです。30人編成のオーケストラをひきつれてツアーしていたころを振り返ると、観客と交流するよりも、観られる存在になっていたんだと思います。バンドの人数を増やして、ツアーでオーケストラを使うのをやめたのは自然な流れでした。我ながら居心地が悪く感じているパターンにしがみつきたくなかった。ステージパフォーマンスは100%向上したと思います。オーケストラは素晴らしかったけれど、枷(かせ)になることもあった。
若い世代はコンサートでもっと開放感を求めていると思うんです。今はステージの上で前より落ち着いているし、バンドと一緒にやるのも本当に楽しい。振り返ると、オーケストラが彩りを添えてくれた曲も多い。でもストリングスを多用しすぎて甘ったるくなってしまった曲もありました。ストリングスは素晴らしい楽器ですけれどね。胸が痛くなるぐらい美しいし」❞
元記事では明示されていませんが、訳文では❝❞をつけた後半部は上述のメロディ・メイカー紙の記事からの抜粋です。ですからこの時点で「今」と言及されているのは70年代後半のロビンとバリーの意見ということになります。
ここで話題になっているオフィシャル・バイオは1979年のスピリッツ・ツアーにタイミングをあわせて全米で発売され、当時アメリカの都市を歩くといたるところの書店に山積みされていました。マンハッタンの華(?)、五番街にある書店バーンズ・アンド・ノーブルにドーンと積まれているのを見たときにはドキドキしたのを覚えています。
<後編に続きます>
{Bee Gees Days}
© 2009 - 2025 Bee Gees Days. 当サイト記事の引用・転載にあたっては出典(リンク)を記載してください。